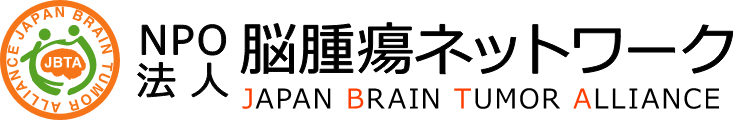体験談 Vol. 8
体験談 Vol. 8
JBTA会員の佐藤剛己です。Zoomミーティングには不精してばかりですが、自身の体調のことと併せて、夏休みの出来事を紹介します。
2020年6月、移住のつもりで2012年3月に渡ったシンガポールで膠芽腫が見つかりました。当時は失語症、失禁、度重なる頭痛があり、妻に連れられてRaffles Hospitalに駆け込み、その日のうちに入院、翌日手術となりました。幸いにも全摘できました。同時に、2019年のS状結腸がんの転移腫瘍が肺に見つかっています。同年7月に帰国、経緯を本にする予定でブログに一年書き続けたものの、お見せした旧知の出版社編集者から「商用出版には乗りません」と言われ、今では書く気力も失せてしまいました。
一方、体調は凄ぶるいいのです。まず四肢の麻痺がなく、てんかんもないので車の運転が従前通り可能です。仕事を続ける上での頭の回転も申し分ありません。今年6月に10年ぶりに車を中古で購入。妻も、年初に取った運転免許を携えて時折運転席に座っています。
電場療法を一時休んで車でこの夏、大阪と愛知県安城市を回ってきました。場所は妻の家族や友達に会う、吉本新喜劇を観るなど、それぞれ理由があってのことですが、それよりも帰国してできた初めての夏の旅行、しかも運転好きの私には車で回れたことが喜びでした。
続いては沖縄へスクーバ・ダイビングに行きました。私はライセンスを取って300本近く潜っているほどのダイビング・ファンです。取った直後の2002年には太平洋ミクロネシアにある「ジープ島」に2回も行き、その時購入した沈船地図のポスターは今の自宅にも飾っています。
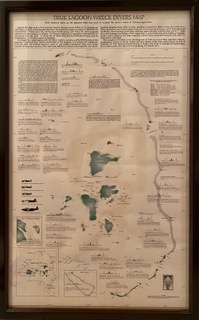
絶対に子供たちをダイバーにすると意気込み、娘はシンガポールで1軒だけある日本人経営のショップでライセンスを取得。なかなか首を縦に振らなかった下の息子も、帰国後に「やっぱり取りたい」と言い出したので、心の中でガッツポーズをしながら、一緒に沖縄へ行きました。
ダイビングを実施するにあたり、あらかじめセカンドオピニオンを取ることは決めていました。Divers Alert Network. Japan(DANジャパン)という、ダイビング事故を医療面から支える世界団体の日本支部があります。リストから、ダイビングに詳しい脳神経外科医を都内に見つけ、今通院している主治医からの紹介状と脳の輪切り画像を手に、その病院に行ってきました。
診察室に入った時のことは今でも忘れられません。パソコンに映した画像と睨めっこしながら「う〜ん」と先生が唸っていたのです。「あなた本当に脳腫瘍?普通は体のどこかに麻痺が出るんだよね」と。結局、潜水は1日2本までなどいくつか約束を守ることを条件にOKを出してもらい、さらに沖縄でご縁のある別の脳外科医を「念の為」と紹介してくれました。直前に、ダイビングで著名なスント(本社フィンランド)のダイブコンピュータを修理に出していたので、先生からの言葉は本当に嬉しかった。
腫瘍持ちになって分かったことがあります。①同じ病名でも人によって症状は異なる、②大事にしたいものはそれぞれ違う、③命には限りがある、です。①は帰国直後に入院した、今通院する本院が成田空港そばにあるのですが、その病室で初めて感じました。当時、私のフロアは脳関係の疾患患者ばかりが入っていて、同室のお隣さんも脳腫瘍。半身に麻痺が残り、時折病室から自宅に携帯電話を掛けていましたが、会話を聞くたびに家庭内の事情が分かって居た堪れなくなりました。
②は数日前の通院で免疫療法室の看護師との会話で改めて気づいたことです。「それぞれ違う」というのは端的に言えば「自己決定権は自分にある」という意味です。私の場合、大事にしたいものは家族と、家族とのつながりです。夏のダイビングだったり、冬のスキーだったり。
肺の転移腫瘍の話をします。私の肺には小さな腫瘍が6こあります。大きいものは現在も10-20mmで推移しています。それぞれが別の「部屋」にあるので、先端医療を含めてどの治療法も「肺を痛める可能性が残る」とのことで、今の家族とのつながりを思うとこれ以上運動機能(肺活量)が落ちるのは勘弁してほしい。どれも決定打はなく、免疫療法で小さくしていく方法を今は選択しています。
③は、生死を左右する病気になった誰もが口にしますが、私は「人はいずれ死ぬという事実に、時間の線引きがあることを認識する」と捉えています。肺の治療経過の話を家族にした際にも、この話をしました。どこへ出しても恥ずかしくない妻は「私は明日交通事故になるかもしれないと思って日々生きてる」と仏様みたいなことを言い、高2の娘は「お父さんをがん患者じゃなく、お父さんとして見てるから」と涙を流して言います。
こんな感動的な言葉をかけてくれる家族があればこそ、彼らのために生き続けたいと思っています。
(佐藤剛己、患者本人)

●JBTAでは皆様の体験談を募集しています。toiawase@jbta.orgまでご連絡ください。
Copyright © JBTA. All rights reserved.