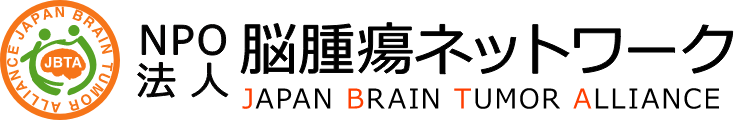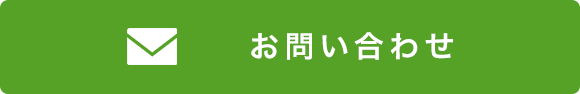体験談(2021)
体験談 Vol.5

私の脳腫瘍がわかったのは、美術系の学校で卒業制作をしていた22歳の冬でした。
当時は地元を離れて一人暮らしをしていました。
午前中に頭痛と吐き気があるものの昼を過ぎると治まる状態が続いて様子を見ていましたが、やがて体調不良で制作にも影響が出始め、気づいた頃には頭の中で心臓が脈動しているような耐え難い頭痛で涙が出たり気が遠のく感覚が表われました。安心材料を得るつもりで念のために町の脳神経外科を受診したところ、脳腫瘍の第四脳室上衣腫であろうということがわかり近くの大学病院に即日入院をする運びとなりました。
私の脳は脳圧が高まって水頭症を起こしていました。歩行しているのが不思議な状態だったようで、入院して安心したのか一気に容体が悪くなりました。ベッドに自分の身体が沈み込んで吸い込まれていくような感覚でした。脳圧を下げるための処置をしたもののあまり症状は改善されず、家族がかけつけた頃にはかなり衰弱した状態でした。
私は、やりたいことをやるために地元を離れ、制作や部活動に明け暮れてあまり親に連絡をしていませんでしたので、家族に与えた急激な心身のダメージは計り知れません。
受け入れがたい深刻な合併症のリスクに私に代わって両親が同意し、準緊急手術が行われました。
複視や眼振、しゃっくりが止まらないなどの手術合併症はありましたが、命拾いしました。
しかし腫瘍は危険な場所にわずかに残っていました。
ここから上衣腫との長い付き合いの人生が始まりました。
気づけばあれから10余年経ち今も私は生きています。取り巻く状況は本当に様々な変化がありましたが、まだ脳腫瘍は完治に至っていません。
手術や放射線による度重なる治療歴の中には、嚥下障害や体幹失調がとても強く出て回復するかどうかわからなかったこともありました。希望を持てなくなったことや、怖いと思うこともありました。闘病はもちろんのこと、病や後遺症を抱えながら健全な精神で人や社会と関わることについては難しさを感じることもありました。私に関わりを持ってくださった多くの人々からの助けに心から感謝をして前向きに活動していることもあれば、再発がわかったりなどで、あらゆることに疲弊して投げやりな気持ちになってしまうこともあります。
しかし、少し冷静になると、いろいろな感情に接する度に「生きていること」を実感します。
そして延ばしていただいた時間の中に、純粋に心から笑っている自分や、何かに単純に喜び感動している自分もまだ確かにあると気づきます。生きていても叶わなかったこともありますが、生きたから叶ったことや、経験や出会いがたくさんありました。
これからもささやかながら自分に関わってくれる人たちや出来事、思いを大切にして、私らしくいられる限り私らしく今日一日を生きていけたらといいなと思います。
(友美さん、患者本人)
JBTAでは皆様の体験談を募集しています。toiawase@jbta.orgまでご連絡ください。
体験談 Vol.4

私は2歳の時に脳腫瘍を発症し、手術しました。
27歳の時に仕事の手順が覚えづらく、ミスが多かったことから、専門病院を受診しました。様々な検査を行い、「高次脳機能障害」と診断されました。
主治医からは、2歳の脳腫瘍の手術の後遺症であると言われました。
「高次脳機能障害」は外見からすると普通に見えますが、社会生活においては、色々と支障が出てくる病気です。
私の場合、複数の事を同時に行いにくい「遂行機能障害」があります。
一度に複数の事を言われると、忘れることが多いのでメモ帳やペンなどの筆記用具やスマートフォンのメモアプリは私の必需品です。小まめにメモをするようにしています。
通院しながら、働き続けるために「就労移行支援事業所」に通所することにしました。
「就労移行支援事業所」は2年という利用期間の定めがあります。その中で訓練を通して、仕事でどのように障害が出やすいのか知り自己理解をして、就職活動をしていく場所です。
私はハローワークに登録して、障害者枠で障害をオープンにして就職活動をしました。仕事において障害が出やすいからです。中には障害をクローズにして就職活動されている方もいらっしゃいます。
障害者枠の求人では、面接で障害について必ず聞かれるので、自分で説明できるように資料作成を行い、面接練習をしてきました。
求人応募した先方から「トライアル雇用」を勧められ、面接をしていただき、採用が決まりました。現在トライアル雇用で働いています。
トライアル雇用は、半年間(場合によっては3カ月)試用期間があり、その後、本採用となるシステムです。今はたくさん覚えることがありますが、小まめにメモを取り、忘れないように仕事をしています。
先方に「トライアル雇用」を勧められて、働き方は多様であること、就労移行支援事業所のスタッフと共に就職活動をして採用が決まったこともあり、人との繋がりは大切にしていきたいと改めて思いました。
JBTAの患者・家族交流会があることで、同じ悩みを抱えた仲間と情報収集ができる場でもあるので、今後も積極的に参加していきたいです。
(園田彩夏、患者本人)
JBTAでは皆様の体験談を募集しています。toiawase@jbta.orgまでご連絡ください。
体験談 Vol.3

「寝ても寝ても、疲れが取れない。いつも眠い。」
そう言い始めたのが、最初の症状でした。30代働き盛りのサラリーマンで、いつも残業ばかりだった夫の訴えを、あまり真剣にはとらえていませんでした。
その後、目の不調、覇気のなさ、物忘れなどの症状が出てくるようになって、やっと病院を受診し、びまん性正中グリオーマと診断されました。
まさか夫が脳腫瘍になるとは想像もしていなかったし、自分ががん患者の妻になることなど考えてもみなかった中での診断に、信じられない気持ちでいっぱいでした。食べ物が喉を通らないという状態を、初めて経験した時期でもありました。何かの間違えだろう、あっさり簡単に治って笑い話になるのだろう、そう思い込もうとしていました。
でも、そんな気持ちが置いていかれるかのように、次から次へと検査や治療が進んでいきました。
怒涛の日々が続く中で、事実と向き合って、少しずつ進むことができるようになったのは、医療従事者の方々がいつも明るく前向きな姿勢で接してくれたことが大きいと思っています。
治療開始前に受けたセカンドオピニオンで「今は始まったばかり。これからできることは、まだ、たくさんある」と言われました。脳腫瘍と診断されたことで全てが終わってしまったような気持ちになっていましたが、治療の始まりがまず第一歩で、ここがスタートなんだと気付かされました。そして、この先生達と一緒にがんばっていきたいと考えられるようになりました。

夫との時間、子ども達にとっては父親との時間が限られているのならば、それを少しでも良いものにすることが、私の目標になりました。
老後になったら夫婦2人でやろうと考えていたことを、数十年前倒しして家族みんなでやったり。今度食べたいと思っていたものを、その日のうちに食べに行くことにしたり。側からみたら生き急いでいるように見えたかもしれませんが、1つでも後悔を残したくないという思いでいっぱいでした。
治療を続けながら、車椅子を押して、スポーツ観戦をしたり、美術館にいったり、家族旅行にも行きました。「ぜひ行ってきて!」「楽しんできてくださいね〜!」と看護師さん達が後押ししてくれたことも、砂浜での車椅子の操作に格闘したことも、最後の家族写真が撮れたことも、とても良い思い出です。
嚥下障害が出てきてからは、「普通のご飯が食べたい」という夫の思いを叶えるために、試行錯誤の日々を過ごしていた時期もありました。栄養摂取について医療者の方と相談をしながら、一体どうするのが良いことなのか悩んでいました。でも、大好きだった豚カツやお寿司をぎりぎりまで食べていられたことは、夫にとっても、私にとっても、よかったと思っています。
少しずつ症状が進んでいく様子を横で見ていることは辛いことでしたが、私が私自身でいられる場所を持っていられたことで精神的に支えられていました。
夫の診断直後に、夫婦共々仕事はやめない方がいいとのアドバイスを受けていました。残念ながら夫は仕事への復帰はできませんでしたが、私は職場の理解を得ながらずっと仕事を続けていました。両立が大変な時期もありましたが、夫の病気や家のことから離れて、自分自身として社会と接していられる場所を保っていられたことは、大きな支えになりました。
夫の闘病は終わってしまいましたが、私のやってきたことが間違っていたのではないかと、もっとできることがあったのではないかと、多くの悔いが残っています。何かやり残したことがあるような気がして、脳腫瘍ネットワークの運営に携わるようになりました。
頑張っていらっしゃる患者さんやご家族の方々に、我が家が経験してきたことを役立ててもらえたらと思っています。
(野村恵子、理事)
JBTAでは皆様の体験談を募集しています。toiawase@jbta.orgまでご連絡ください。
体験談 Vol.2

次女はるかの体調に異変が起きたのは、6歳の時でした。朝起きると「頭が痛い」「気持ちが悪い」と訴えるものの、日中は元気に過ごす時期が続いていました。幼稚園の先生から「転ぶことが増えた」と指摘されたのもこの頃。次第に、はるかが右足を引きずっていることに気付きました。しかも、右手に力が入らない様子。「おかしい」胸がざわつきました。
総合病院へ連れて行ったところ、脳幹グリオーマ(DIPG)と診断され、余命半年と宣告されました。
最初はなかなか、病気を受け入れられませんでした。有効な治療方法はなく、在宅療養で、家族で過ごせる時間を大切にすることを医師にすすめられましたが、「あきらめなさい」といわれたようで、悔しくて仕方ありませんでした。激しく動揺し、いらだちと絶望感に襲われました。自ら治療法を探そうと、全国を駆け回ったり、わらにもすがる思いで、あらゆる手段を尽くしました。一分一秒でも長く生きて、そばにいてほしいと願っていました。
「お泊まりに連れて行ってほしい」。それがはるかの最後の望みになりました。その願いをかなえようと、家族で千葉県へ旅行に行きました。時間が許す限り家族との思い出を作り、はるかの喜ぶ顔が見たかったからです。
「頭が痛い」。旅行からの帰り道、はるかは訴えました。翌日、病院へ行くと、そのまま入院。帰宅して間もなく、医師から「容体が急変し、呼吸が止まった」と電話で告げられました。人工呼吸器で延命措置をしたが、意識が戻ることはありませんでした。意識が戻らないまま、死に一歩一歩近づくにつれ、少しずつ弱っていきました。これ以上、幼い体を縛りつけたくないと、人工呼吸器を外すことを決断したのは、倒れてから約2週間後のことでした。今振り返ると、医療従事者の寄り添いがあったからこそ、(外すことは)間違いではないと判断できたのだと思います。
3歳上の長女とはるかには、病名はもちろん、死が迫っていることを伏せ、「頭におできができたんだよ」とだけ伝えていました。服薬の影響で腫れてしまった顔を「面白い」と笑い、右手にまひが出ても、左手で上手に箸を使えるようにもなりました。亡くなるその時まで常に生きる楽しみを見つけ、成長し続けていたのです。
はるかと過ごした日々が後年、子どもの成長や楽しみを支える施設である「こどもホスピス」を作りたいという考えにつながりました。

「ホスピス」と聞くと、治る見込みのない人が最後に死を待つ場所、というイメージが強く、わが子を送り出すことに抵抗を覚える親も多いかもしれません。しかし「こどもホスピス」は、子どもたちの「生」を支える施設なのです。患児の多くは、入院や通院のために家族や友達と引き離され、通学や習い事、旅行や遊びなども思うようにできなくなってしまいます。「こどもホスピス」は、病気の子どもたちに楽しみや学びの場を提供し、実り多い生活を送ってもらうための「お家」なのです。
告知後、病に苦しむ子どもに向き合うことも、親にとっては並大抵の苦労ではありません。「こどもホスピス」は親たちが心身のケアを受け、休息する施設でもあります。
「ちゃんとやれるか、試されているのかな。」と感じながら、娘に導かれる形で、「夢」の実現まであと一歩というところです
(田川 尚登、副理事長)
JBTAでは皆様の体験談を募集しています。toiawase@jbta.orgまでご連絡ください。
体験談 Vol.1
NPO法人日本脳腫瘍ネットワーク「JBTA」の理事長のガテリエ・ローリンです。
私はベルギー人ですが、 日本に暮らして15年以上になります。
がんが見つかったのはいつですか。

2016年に悪性の脳腫瘍と診断されました。1年前から手足のしびれがあり病院を受診しましたが、そのときは診断がつきませんでした。
しばらくして、出張中にカートが手から落ちてしまうことがあったんです。何もないだろうと思いつつ再度診察を受けると、「脳に8cmの腫瘍がある」とのことでした。
その後、覚醒下手術を2回と放射線治療を受けましたが、腫瘍が残っているため現在も化学療法を続けています。
母国ではない国での治療に不安はありませんでしたか。

母国のベルギーと日本の治療法を調べると、どちらも高い水準であることがわかり、大きな不安はありませんでした。幼い子供もいたためベルギーに帰ることはできず、母に来日してもらうことにしました。
手術は、看護師や言語聴覚士などと会話をしながら、脳の機能が損なわれていないことを確認しつつ、ギリギリの範囲まで腫瘍を摘出します。私の場合、日本語、フランス語、英語の3言語の確認が必要だったため、手術に立ち会える人を探すのが大変でした。
活動を始めたきっかけを教えてください。
私の脳には、取りきれなかったがんが残っています。いつどうなるかわからないし、動けるときに動きたい。「できることはやったと言いたい」と思い、JBTAでの活動を始めました。がんと共に生きることで、国内外のがん患者を取り巻く社会たのめに、より貢献したいと思っています。
悪性脳腫瘍は、希少がんと呼ばれる非常にまれながんなので、進んだ研究と治療法の確立が望まれています。海外ではどのように研究が進められていて、どんな薬があるのかを学ぶために、国内外の学会に参加したり、情報収集を行ったりもしています。日本だけでなく、アジア諸国や欧米のアカデミア、製薬業界、規制当局および患者団体との協力関係を強めることで、さらなる前進に至ると信じています。
JBTAは、患者・家族での交流や情報交換のほか、患者が積極的に治療に参加していけるように、医療従事者などとのネットワークの構築も行っています。患者さんは、自分たちの人生の質を高めるために、もっと思いを声に出す必要があると思っています。そうしやすい環境を作っていきたいですね。皆さんも、自分の声が届けられる場所をぜひ探してみてください。
(ガテリエ・ローリン、理事長)
JBTAでは皆様の体験談を募集しています。toiawase@jbta.orgまでご連絡ください。


一覧に戻る ≫